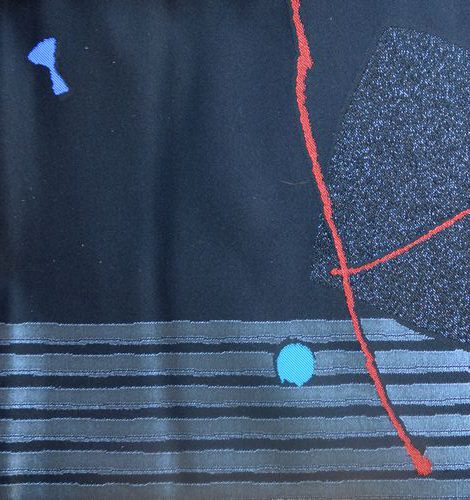おしゃか様の日常につぶやかれた言葉など、普段の生活の中でどのようなことをおっしゃっておられたかを集めた感興のことばなどを拝見しますと、おしゃか様のお人柄がしのばれます。お経で拝見するとおりの生きとし生けるものへの限りない愛情に満ちておいでです。わたしの仏教との接点は、ある僧侶の方にお目にかかり、毎月一度自宅へお越しいただき、いろいろなお話を聞かせていただいた十数年の経験だけです。東北大学のインド哲学から雲水経験を経られて、真言密教に進まれ、葬式坊主になることを嫌われ、独立して布教をなされていました。いろいろなお話をお教えいただいたのですが、「仏教とは、子を抱いた母の姿です」とたびたびおっしゃられておいででした。いまさらに深い意味があるんだな・・・と感じています。おしゃか様は「八聖道」という行動の規範を残しておいでですが、わたしにははるかに遠い規範ですし、説明もできるレベルではありません。でも、在家信者にも実行できる「十の善行」はなんとか近づける規範ではないかとおもえますので、書き出してご覧いただきます。1、生き物を殺すこと。2、与えられないものを取ること(盗み)。3、配偶者以外との性行為。4、虚言。5、中傷の言葉。6、粗暴な言葉。7、軽薄な駄弁。8、欲求。9、害意。10、誤った見解。の十です。仏教では意思とその表現である行為をとても大切にいたします。すべてが「前世で行われたことを原因とする」という運命論、「主宰神による創造を原因とする」という主宰神論、すべては偶然であるという偶然論などは仏教では認められません。自身の意思でなす行為の意味がなくなってしまうからです。他律の世界ではなく自律の世界で心を正し、倫理性を高めて生きてゆくことが、自分の将来を明るく楽しくしてくれます。繰り返しそのようにおしゃか様は語りかけていただいたのだとおもいます。「他の人が何をなさなかったかを語ってはいけない。自分が何をなさなかったかを思うことです。」 わたしなんかは自分の生存への渇望を呼ばれる心の奥底にある生存への盲目的な執着に気もつきませんし、気が付いてもその執着を克服しようなんて思いつきもいたしません。でも、おしゃか様は気が付き、瞑想をともなって克服なさっておられます。「切っても切っても根っこが張っていて・・・」と併記されていたように記憶しています。つまり、あらゆる制約を克服なされた精神的に真の自由な方だったのではないのでしょうかと想像しています。