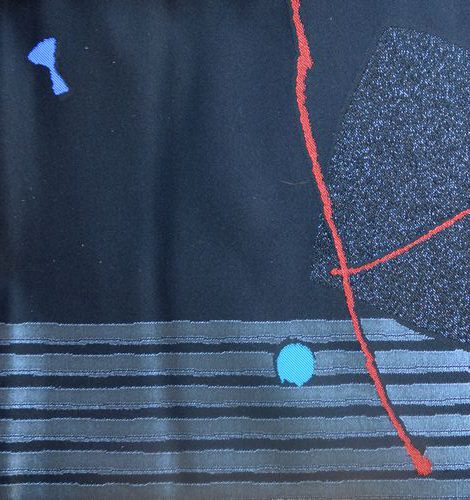
おしゃかさまはお経(「律蔵」「大品」)の中で次のように述べておいでです。”さて、托鉢修行者たちよ、これが苦の原因をなす、高貴な者たちにとっての真実(苦集聖諦)である。それは再度の生存へみちびく、喜びと熱望をともない、あちこちで歓喜するこの渇望である。すなわち、快楽への渇望、生存への渇望、無生存への渇望である。”
また、同じ内容を縁起説から見て、”渇望という原因から執着が生じ、執着という原因から生存が生じる”と述べておられます。
では、渇望とは何を欲することなのでしょうか。阿含のお経の中で、三つあげられています。第一の快楽への渇望は、性的衝動に代表される感覚的快楽を追求する欲望である。第二の生存への渇望は感覚的な欲望ではなくて、生存そのものを渇望する衝動です。三の無生存への渇望とは、死によってすべて消え去ることを渇望する衝動です。
縁起説ではこの渇望から執着が生じ、さらに生存を作り出すと説明されています。その執着の対象は1、快楽、2、誤った見解、3、誤った習慣と誓戒、4、自己(または自己があるという見解、)の四つを挙げておられます。おしゃかさまは渇望が執着を生み、執着が生存を促すと説かれたのです。
まもなく終着駅です。バラモン教やジャイナ教、唯物論の主張と異なる点、同じ部分などの比較を通して、仏教の世界が少し見えてくるかもしれません。







